こちらも幸せな披露宴
2012.10.13 Saturday | よんなん的日常
 早大鉄研の同期(♀)と後輩君の披露宴に招かれて行って来ました。
早大鉄研の同期(♀)と後輩君の披露宴に招かれて行って来ました。社会人になって8年経って、こんな人付き合いでもいちおう片手で数え切れるか余るかくらいの回数は披露宴に呼ばれました。
(片手でも31まで数えられるというツッコミは却下)
社会人になりたての頃は、いかにも式場のプランナーに勧められるがまま感満々の「新郎新婦が1日限りの芸能人気分」的な披露宴に辟易しましたが、ここ数年は(少なくとも自分の周りでは)文字通り「新郎・新婦が結婚したことをお披露目する」(+日ごろの感謝を述べる)雰囲気のが、主流になっているような気がします。
きょうの披露宴もそんな感じので、一応はチャペルでの挙式、披露宴でのケーキ入刀、キャンドルサービス、後輩諸君による余興…という一連のイベントがあった程度で、特に今回は新郎も新婦も知っている間柄だったこともあって、出席したこちらもめでたいよい気分で帰ってきました。
あ、「新婦側友人代表」では私がお祝いの言葉を述べました。(ささやかな自慢)
 一番上の写真はキャンドルサービスの写真ですが、これはローソクではなく、新郎と新婦がそれぞれ持っているポット状の容器から透明な液を注ぎ合わせると光り始める面白い演出。
一番上の写真はキャンドルサービスの写真ですが、これはローソクではなく、新郎と新婦がそれぞれ持っているポット状の容器から透明な液を注ぎ合わせると光り始める面白い演出。周囲は「何?」「不思議ー」的な反応でしたが、ごく一部の我々はすぐに「サイリウムの原理だ!」「王国民か!」などとダメ発言。(ぇ
のちに下記の酔っ払いが触ってこぼしたのが手にかかってましたが、大丈夫なのかな……。
それはそうと新婦は数年間、早大鉄研の紅一点だったので多方面から人気があり、今回の披露宴に際しても招待客はかなり人選をしたようですが、宴とお酒が進むにつれて
「△△さんはなんで○○君なんかと結婚するんだー」
的に荒れ始めたのが一人いて、新郎君も居酒屋での2次会で「意外なところにライバルがいました」と漏らしていたのを聞き逃しませんでしたぞ。
 いわゆる「結婚式の2次会」は特に設定されず、上記の通り居酒屋に場所を移しました。
いわゆる「結婚式の2次会」は特に設定されず、上記の通り居酒屋に場所を移しました。最初は、早大鉄研側で残った面々で始めましたが、新郎が大学院(商学研究科)の同期と新婦を連れてやってきましたよ。
理工出身の当方は「院の同期」と聞くと「ゼミ(or研究室)の同期」かと思っちゃうのですがゼミは別々の研究科全体の同期だそうで、文系の大学院は人数が少ないとはいえこんなに仲がよいのが意外です。
あと、修士課程のあとの進路でサラリーマンは第二志望だったという具合の人が多かったのも、修士課程修了で就職するのが前提のように進学する理工との違いを感じました。
で、最初は全然知らない人ばっかりだしな〜と思ってたのが、先方にいた汽車旅愛好会出身の某氏がうまいこと仕切ってすっかり打ち解けて楽しい時間を過ごせました。
そういう場を作れるあたり、鉄研と汽車旅愛好会の違いですかねー。
 新婦はサークル内で紅一点だったばかりか、誰にでもやさしいので上記のようにいろいろ勘違いした人が少なくとも数名いるのですが、2次会で新婦が語ったところによれば
新婦はサークル内で紅一点だったばかりか、誰にでもやさしいので上記のようにいろいろ勘違いした人が少なくとも数名いるのですが、2次会で新婦が語ったところによれば「他の人がそう思ってアプローチしていたことにまったく気がつかなかった」
だそうで、結婚式の日に「新郎以外は眼中になかった宣言」を聞かされると、これはもう「2人揃って末長く爆発しろ!」(←祝福の言葉)以外の何物でもないですよ!
おめでとうございます。
 先々週の金曜に、電車の車内広告で見つけて「これだ!」と思いました。
先々週の金曜に、電車の車内広告で見つけて「これだ!」と思いました。 1062円で我が家に無線LAN環境ができました。
1062円で我が家に無線LAN環境ができました。 我が母校(中学・高校)の学園祭があったので、顔を出してみました。
我が母校(中学・高校)の学園祭があったので、顔を出してみました。 大手商社主催のファミリーセールの招待状をもらって、東京ビッグサイトに来ました。
大手商社主催のファミリーセールの招待状をもらって、東京ビッグサイトに来ました。 さて、やってきたバスは「
さて、やってきたバスは「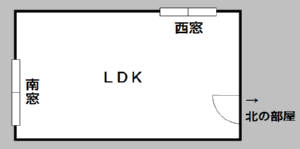 夏も終わろうかという頃になって、やっと表題の単語を思い出したのでありましたよ……。
夏も終わろうかという頃になって、やっと表題の単語を思い出したのでありましたよ……。 帰りの電車で読んでいて、久々に作品に夢中になって降りる駅を乗り過ごしました。
帰りの電車で読んでいて、久々に作品に夢中になって降りる駅を乗り過ごしました。