「披露宴の司会」というお仕事体験(2年ぶり2回目)
2013.07.27 Saturday | よんなん的日常
 大学の先輩の結婚披露宴があり、司会を務めました。
大学の先輩の結婚披露宴があり、司会を務めました。前回(2年前)、知人の披露宴で司会をしたとき「プロと大して変わんない」と評してくれた先輩です。
場所は、栄えある「帝国ホテル」です。(←打ち合わせでこんなこと書いといて言う人)
披露宴の司会、というとそれなりの技量を要求されるように見えるかもですが、事前準備の面では、台本は前回のものを再構成して、さらにプロの方に2度ほど添削をお願いし、披露宴独特の「忌み言葉」の言い換えや、司会からのプロフィール紹介文の組み立てなど、プロの知恵をお借りしました。
披露宴当日のタイムキーパー役は式場側のチーフ(「キャプテン」と呼ぶ式場もある)がすべて取りしきってくれるので、司会は進行の度合いを特別に気にする必要もなく、式場スタッフが出してくれるCueとともに、添削済みの台本を読み進めていけば滞りなく終わる……なんて、手の内を明かしてみたり。
……もちろん、「用意された原稿を、話すように読む」というアナウンサーのような技能も少し必要ですが、そこは「昔取った杵柄」で自称セミプロ級です。
で、「友人司会」として世間並み程度のお礼をいただいて、添削をお願いしたプロの方に添削代を包んでみると、はて、プロの司会代ってのは(払う側には)確かにばかばかしいよな、と、ふと思ったりするわけです。……式場紹介だと7〜10万円取られます。
「プロの仕事」を期待するのは、披露宴独特の言い回しを使い分ける(知っている)ことであったり、新郎新婦のプロフィール紹介文を作る技量、だと私は思うのですが、今回のようにここを「添削代」として金額に換算すると、司会代相場の10分の1程度なのです。
(ただ、私の場合、添削をお願いしているのが学生時代の先輩なので「お知り合い価格」なのかもしれません、、、)
あとは、台本にない突発事象が起こったときの対応力、という点もありますが、ここに長けているのは「プロ」といってもよほど場数を踏んだベテランの域でしょうし、それに司会の腕もさることながら、式場のチーフをはじめとするスタッフの力にもよります。
腕のよいチーフが仕切る披露宴ならば、そもそも突発事象が起きても来賓に「突発事象」だと気づかれない程度のものにしてしまうはずです。……なにしろ、事前に用意してある進行表(≒台本)の中身を知っているのは新郎新婦・式場・司会だけなのですから。
ちなみに今回の披露宴で台本になかったことといえば
(1)新婦母が急きょ欠席となり、新婦の親が関係する場面で「ご両親」という言葉を言い換える必要が発生した
(2)帝国ホテル名物の「炎のデモンストレーション」でアナウンスを入れるタイミングが、事前打ち合わせでの式場側プランナーの話と当日打ち合わせでのチーフの指示が違った
(3)肉料理を冷めないうちに食べてくれ、とアナウンスするよう式場側から依頼された
(4)司会からのプロフィール紹介で新郎新婦と詰めた中身以外の(できれば伏せたかった)ことを来賓代表が挨拶でしゃべってしまった
くらいです。……(1)には困りましたがチーフを始めスタッフの方々の助言をいただくことができましたし、(4)は涼しい顔をして華麗にスルーです。
もちろん、プロに頼む場合、事前準備と当日の拘束時間のわりに高い報酬(代金)とはいえ、結婚式場なんて平日は閑古鳥な業界ですから、専業でやっている人に頼むならば、式場の取り分も考えると確かに式場が要求する額くらいは支払わないと、その人のメシの種になりません。
……ということを考えると、披露宴専業でなくMCや司会業を手広くやっているフリープロ(披露宴司会は副業のような位置づけの人)を探してお願いするか、私のような「友人」に頼んでしまうのが“賢いお買い物”といえそうです。
#フリー司会者はgoogle先生に「フリー司会」とか「フリーMC」とか「フリーアナウンサー」とか聞けばたくさん教えてくれます
最後に、個人的な備忘録として今回の反省点を書き残しておきます。
(1)祝電の下読みをしなかったので、読めない固有名詞があった(←最悪)
(2)新婦友人挨拶の紹介を、直前の新郎友人挨拶が終わったときの拍手が鳴り止まないうちに始めてしまい、拍手にかき消された(→新婦友人の肩書きが立派なので新郎親族にハッキリ聞かせること、という事前打ち合わせだった)
(3)オープニングの「新郎新婦の入場です!」は(声量は出たけど)やはり緊張していた(→所詮はアマチュア司会)
逆に言うと、プロとアマチュア(自称セミプロ)の品質の差は(我ながら)この程度、と自負しています。……次に頼んでくれる知人がいたら、祝電はちゃんと紹介の前に一度読んでおきます。。。
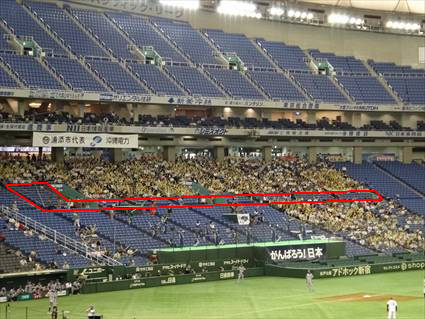
 ……が、「制服応援」はJR東日本も取り入れ始め、マニア垂涎の応援グッズは年々しょぼくなったうえ、チームも弱くなり(今年も1回戦敗退)、すっかり魅力がなくなりました。。。
……が、「制服応援」はJR東日本も取り入れ始め、マニア垂涎の応援グッズは年々しょぼくなったうえ、チームも弱くなり(今年も1回戦敗退)、すっかり魅力がなくなりました。。。 きのう、新宿駅南口からしばらく歩いたところに、バスの乗降場ができていました。
きのう、新宿駅南口からしばらく歩いたところに、バスの乗降場ができていました。 書斎兼寝室(という名の引きこもり部屋)には、前の住人が置いていった「門型」の収納棚が鎮座しています。
書斎兼寝室(という名の引きこもり部屋)には、前の住人が置いていった「門型」の収納棚が鎮座しています。 年度末35歳、と勤務先の福利厚生制度で(定期健康診断の代わりに)人間ドックを受けられる歳になり、初めて受けに行ってきました。
年度末35歳、と勤務先の福利厚生制度で(定期健康診断の代わりに)人間ドックを受けられる歳になり、初めて受けに行ってきました。 我が家は洗面所の入口がドアだったんです。(中古で買った時のまま)
我が家は洗面所の入口がドアだったんです。(中古で買った時のまま)
 一つ問題になったのは、ドアの内側がタオル掛けだったことです。
一つ問題になったのは、ドアの内側がタオル掛けだったことです。 大学生の頃だったか以来、それまで「金銭出納帳」とか「こづかい帳」として売っているノートをやめて、それっぽいエクセルの表を作ってパソコンでつけていました。
大学生の頃だったか以来、それまで「金銭出納帳」とか「こづかい帳」として売っているノートをやめて、それっぽいエクセルの表を作ってパソコンでつけていました。