久々に実家へ郵便物を受け取りに行きました。
実家の滞在はそこそこに、周辺をぶらぶらして帰ります。
新浦安といえば、先の大震災で液状化被害がひどかったエリアでもあります。
幸い、我が実家は何の被害もなかった(しばらくガス・水道が止まっただけ)のですが、近所では家ごと傾いたり、家は無事でも塀が傾いたり、庭が土砂で埋まったりしたところがありました。
この界隈は大手不動産会社による建売の分譲宅地で、傾いたところは分譲当時の建物ではなく最近建て替えたところが目立つのですが、建て替えていないお宅でも隣が傾いたあおりを受けたように見受けられるところもあり、さまざまです。

発災から8ヶ月が過ぎ、足場に囲われた家(補修中?)、取り壊された家、建て替えが進んでいる家、ジャッキアップしている家(写真)、放置されている家、いろいろです。
ただ、もともと建売の分譲地で行政当局の指導もあって「まちなみ」は統一感が取れていたのが、建て替えが集中しているあたりは見た目が一気にバラバラになってしまった印象で、これはかなり残念です。
一番痛いのは、全戸垣根だったところへ、建て替えに際して垣根を撤去して塀にする家です。……これは本当に目立ちますし、各戸がバラバラなデザインの塀で敷地と道を隔てているのは従前と比べて景観を損ねている印象を受けます。
地域協定があればよかったんですが、ちょうど、変なふうに建て替える家も出てきたし(写真の家もそう)そういうの作ろうよという話が自治会で出ていた矢先の震災だったので、これだけ一気に建て替えが進んでしまうのは、本当にもったいないです。
#写真のジャッキアップ中の家も、庭と垣根をなくして敷地いっぱいに家を建てて共同住宅(3戸)にしている

さて、近所にある1979〜1980年に建てられた“公団”の賃貸住宅は、すっかりリニューアルして見違えるようになってました。
(このリニューアル自体は震災とたぶん無関係)
築30年、おまけに旧耐震基準時代の建物とあって、分譲の中古マンションでも「築古マンション」と敬遠されるような世代のマンションです。……小学生のとき友達が住んでいて住戸の中に入れてもらったこともありますが、当時のままだとすれば相当陳腐化しているはずです。
まだリニューアルされていない号棟もあるので見比べると分かりますが、外から見える部分だけでもこんなに変わるものかっ!! と思わされます。
現在の“公団”である都市再生機構の「
リニューアルi」というプロジェクトのようで、1970年代築のマンションも捨てたもんじゃないな、と思いましたよ。
ただ、分譲マンションだとこれだけ大胆な共有部分の改装は管理組合の意思決定がもたつくでしょうし、賃貸ではこれだけ大規模なファミリー向け住宅を経営している民間の業者なんてないですし(民間だとどうしても面積あたりの家賃単価が高いワンルームマンションばかり建てる傾向がある)、公団のパワーというものを感じました。。
 大学野球シーズンもようやく終わり、応援マニアの活動は、吹奏楽団の定期演奏会や応援団祭へと移っていきます。
大学野球シーズンもようやく終わり、応援マニアの活動は、吹奏楽団の定期演奏会や応援団祭へと移っていきます。 船橋稲門会の日色君に誘われて行ってきました。
船橋稲門会の日色君に誘われて行ってきました。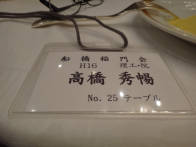 その後、懇親パーティー(立席ではなかった)を経て解散です。
その後、懇親パーティー(立席ではなかった)を経て解散です。 都市対抗野球で東京ドームへ行くと手荷物チェックがあって、ビン・カン・ペットボトル飲料は入場後に紙コップへ移すよう言われます。
都市対抗野球で東京ドームへ行くと手荷物チェックがあって、ビン・カン・ペットボトル飲料は入場後に紙コップへ移すよう言われます。 上野の東京障害者職業センターは、東京メトロの上野検車区の隣に建っているオフィスビルに入居しています。
上野の東京障害者職業センターは、東京メトロの上野検車区の隣に建っているオフィスビルに入居しています。 今月中は午後が自由なので、池袋へ行ってサンシャインシティの会議室で行われていた「
今月中は午後が自由なので、池袋へ行ってサンシャインシティの会議室で行われていた「 発災から8ヶ月が過ぎ、足場に囲われた家(補修中?)、取り壊された家、建て替えが進んでいる家、ジャッキアップしている家(写真)、放置されている家、いろいろです。
発災から8ヶ月が過ぎ、足場に囲われた家(補修中?)、取り壊された家、建て替えが進んでいる家、ジャッキアップしている家(写真)、放置されている家、いろいろです。 さて、近所にある1979〜1980年に建てられた“公団”の賃貸住宅は、すっかりリニューアルして見違えるようになってました。
さて、近所にある1979〜1980年に建てられた“公団”の賃貸住宅は、すっかりリニューアルして見違えるようになってました。 きょうから、上野の障害者職業センターへ毎日通所することになりました。
きょうから、上野の障害者職業センターへ毎日通所することになりました。 所用で川崎へ行きました。
所用で川崎へ行きました。