ニニウという集落と公立学校
2011.05.28 Saturday | よんなん的戯言
 きのう北海道の石勝線で起こった特急列車の脱線・火災事故で、事故現場となった「第一ニニウトンネル」(ここ)という文字で久しぶりに「ニニウ」という地名を目にしました。
きのう北海道の石勝線で起こった特急列車の脱線・火災事故で、事故現場となった「第一ニニウトンネル」(ここ)という文字で久しぶりに「ニニウ」という地名を目にしました。夕刊でしかもトップではないとはいえ、一面で「ニニウ」の文字を目にするとは……。
北海道の占冠村にある無人の集落「ニニウ」は、「ニニウへ急げ!」という特集サイトがあるほど、知る人には知られた場所です。
自分も、昨年の秋に北海道へ行った際にぜひ立ち寄ってみたいと思っていましたが、あいにく道路が災害通行止めで行くことはかないませんでした。
……現在も通行止めのはず(参照→胆振管内・上川管内)で、消防・警察・報道・そしてJRはどうやって現地入りしたのか分かりませんが、ニニウへ陸路で入るには道道610号線〜136号線のルートしかありません。ニコニコ動画に2009年時点の走行映像がUPされています。(その1・その2)
(事故現場に隣接する清風山信号場=ニニウ駅になるはずだった場所へは「その2」の動画の0:51付近に見える分岐路を左折する)
国道ではない道道とはいえ、立派な悪路です。。。
事故の原因究明や復旧は関係各者の仕事で自分がどうこういう話ではないニュースなのですが、そんなわけで個人的に以前から(中学3年の春休みに北大へ進学した中高鉄研の先輩から「ニニウ」という地名を聞かされてから)注目していた「ニニウ」がニュースに出てきたものですから、久しぶりに「ニニウへ急げ!」を読んでみました。
集落がなくなって住民がいなくなると地名もなくなる例もあるんですが(例:北海道下川町の下川鉱山は閉山とともに住民がいなくなったので集落の地名「ペンケ」が消えて隣の「班渓」にまとめられた)、ニニウは住人がいなくなっても地名がそのままです。
#なんと郵便番号まである!(日本郵政のページ)
「ニニウへ急げ!」のこのページによると集落がなくなったのは昭和49年度いっぱいで「新入(ににゅう?)小中学校」が閉校したことが直接的なきっかけだったようです。
……公立学校の閉校で集落が消えた例といえば、去年の秋に訪れた志美宇丹が記憶に新しいです。
いまも昔も、学校が限界集落の防波堤になっているんだなぁと思いました。
集落の戸数が少なくなっても、せめて公立小学校さえあれば校長・教頭・クラス担任の3人が赴任(=3世帯が定住)します。中学校もあればさらに科目別の教員も赴任します。
教員が集落から去ると、給与所得者が一気に減った集落から次は郵便局がなくなります。郵便局は集落で唯一の金融機関でもありますから、郵便局がなくなると現金を引き出せなくなります。……集落での生活が一気に困難になることは想像に難くありません。
志美宇丹とは峠を一つ越した仁宇布では集落の子が軒並み学校卒業の年齢に近づくと「山村留学」と銘打って都会から生徒を呼び集めて学校を維持してきました。……教員が残っただけでなく、山村留学に来た子とその親が定住するケースも出始め、集落の人数も増えているようです。
山村留学はあまり成功している事例がないようですが、住民が引き続きその地での生活を望むなら、小中学校に通う世代の子を産むなり国内海外問わず留学生を呼ぶなり、なんとしてでも学校を維持するのは効果が大きいでしょう。
一方で、和寒町福原のように小学校がなくなり郵便局もないのに集落で生活が続いている例もあるにはあります。一つとなりの集落(和寒町西和)まで6kmくらい、町中心部までも15kmくらいしか離れていないのと、旭川に比較的近いからでしょうか?
「ニニウへ急げ!」でも触れられていますが、ニニウで残念なのは、集落が無人になってから鉄道が通り(駅の設置予定はあったので信号場になった)、送電線が通り、そしてついに高速道路までが通る(2011年秋開通予定)ようになったことです。
ニニウのために作られた鉄道や送電線や高速道路ではなく、その先に帯広や釧路、根室という都市があるからなのですが、なんとももったいない話です。
 最初におことわりをしておきます。この文章を書いているのは、仕事にも行けずに毎日「自宅警備」をしているような人間です。
最初におことわりをしておきます。この文章を書いているのは、仕事にも行けずに毎日「自宅警備」をしているような人間です。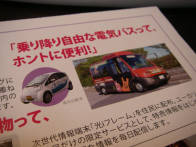 新聞折込にユーカリが丘の宅地分譲チラシがあって、なんだか見覚えのある「電気バス」の写真が載っていました。
新聞折込にユーカリが丘の宅地分譲チラシがあって、なんだか見覚えのある「電気バス」の写真が載っていました。